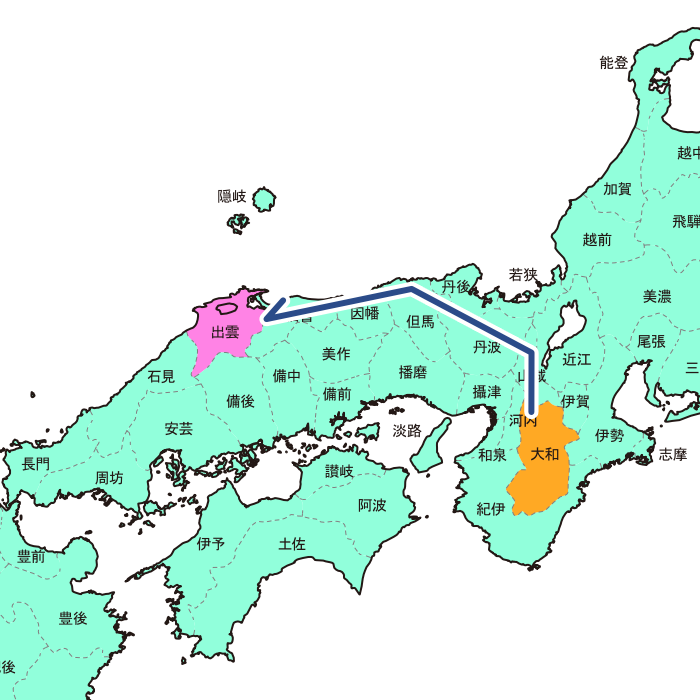出雲の国風土記 「意宇の郡」 総記

原文
意宇郡
合 郷壱拾壱[里卅三] 余戸壱 駅家参 神戸参[里六]
母理郷 本字文理
屋代郷 今依前用
楯縫郷 今依前用
安来郷 今依前用
山国郷 今依前用
飯梨郷 本字云成
舎人郷 今依前用
大草郷 今依前用
山代郷 今依前用
拝志郷 本字林
宍道郷 今依前用 [以上壱拾壱郷別里参]
余戸里
野城駅家
黒田駅家
宍道駅家
出雲神戸
賀茂神戸
忌部神戸
宍道郷 今依前用 [以上壱拾壱郷別里参]は、古写本宍道郷 今依前用 [以上壱拾郷別里参]との記載あり。
現代語訳本文
意宇の郡。
合計で、郷11(里33)・余戸1・駅家3・神戸3(里6)
母理の郷。もとの字は「文理」
屋代の郷。今も前のままの字を使用している。
盾縫の郷。今も前のままの字を使用している。
安来の郷。今も前のままの字を使用している。
山国の郷。今も前のままの字を使用している。
飯梨の郷。もとの字は「云成」
舎人の郷。今も前のままの字を使用している。
大草の郷。今も前のままの字を使用している。
山代の郷。今も前のままの字を使用している。
拝志の郷。もとの字は「林」
宍道の郷。今も前のままの字を使用している。(以上の11の郷は、郷ごとに里が3つある)
余戸里
野城駅家
黒田駅家
宍道駅家
出雲神戸
賀茂神戸
忌部神戸
各地名の読みに関しては、この後の解説欄にて詳しく。
概略
この節は、意宇の郡にある11か所の郷の名と字の変更、および、駅家や神戸についてのリストとなっている。
解釈・解説
地名の読み一覧
意宇の郡:おうのこほり
母理:もり
屋代:やしろ
盾縫:たてぬひ
安来:やすき
山国:やまくに
飯梨:いひなし
舎人:とね
大草:おほくさ
山代:やましろ
拝志:はやし
宍道:ししぢ
余戸:あまりべ
野城:のぎ
黒田:くろだ
宍道:ししぢ
出雲:いづも
賀茂:かも
忌部:いむべ
意宇の郷
「おうのさと」と読む。
意宇郡に存在する郷などの合計について
原文
意宇郡
合 郷壱拾壱[里卅三] 余戸壱 駅家参 神戸参[里六]
口語訳
意宇の郡。
合計で、郷11(里33)・余戸1・駅家3・神戸3(里6)
郡・郷・里・余戸
郡・郷・里・余戸・駅家・神戸
駅家・神戸
郡・郷・里・余戸・駅家・神戸
意宇郡の郷について
原文
母理郷 本字文理
屋代郷 今依前用
楯縫郷 今依前用
安来郷 今依前用
山国郷 今依前用
飯梨郷 本字云成
舎人郷 今依前用
大草郷 今依前用
山代郷 今依前用
拝志郷 本字林
宍道郷 今依前用 [以上壱拾壱郷別里参]
余戸里
口語訳
母理の郷。もとの字は「文理」
屋代の郷。今も前のままの字を使用している。
盾縫の郷。今も前のままの字を使用している。
安来の郷。今も前のままの字を使用している。
山国の郷。今も前のままの字を使用している。
飯梨の郷。もとの字は「云成」
舎人の郷。今も前のままの字を使用している。
大草の郷。今も前のままの字を使用している。
山代の郷。今も前のままの字を使用している。
拝志の郷。もとの字は「林」
宍道の郷。今も前のままの字を使用している。(以上の11の郷は、郷ごとに里が3つある)
余戸里
もとの字と前のままの字
母理郷 本字文理や飯梨郷 本字云成の部分、これは和銅6年(713年)の「諸国郡郷名著好字令」や総記末尾に記載のある「神亀三年の民部省口宣」(726年)によって字を替えたという履歴を示す。
もっとも、ここに記載の内容と、各郷の説明書きに記載の内容に揺れがあるものもあり、いずれを誤りとするかに諸説あり。
その他施設などについて
原文
野城駅家
黒田駅家
宍道駅家
出雲神戸
賀茂神戸
忌部神戸
口語訳
野城駅家
黒田駅家
宍道駅家
出雲神戸
賀茂神戸
忌部神戸
当該名称の駅家や神戸があったことを示している。
次:
出雲の国風土記 「意宇の郡」 (2) 国引き神話 (上)
「出雲の国風土記」の「意宇郡」後半の原文と現代語訳、ならびに一般的解釈です。いわゆる「国引き神話」に関する記載があります。
前:
出雲の国風土記 「総記」
「出雲の国風土記」の冒頭「総記」部分の、原文と現代語訳、ならびに一般的解釈です。出雲国の大きさや、その名の所以、ならびに国内の神社の総数と郡のあらましが記載される。